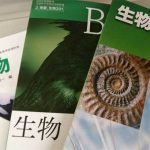理科の配点が高い医学部
理科の得点配分は大学によって違いますが、理科が得意な人の場合、少しでも配点比率が高いほうがいいですよね。
もし他の科目で点を落としても十分カバーできますし、他の科目を頑張れば得点率を上げられます。
問題は配点が高い大学医学部はどこなのか、という点に尽きますが、代表的なのは以下の5つです。
- 広島大学
- 大分大学
- 鹿児島大学
- 帝京大学
- 自治医科大学
国立と私立、それぞれで理科の配点が高い大学があります。
物理とか化学、生物が好きな人は、ぜひ受験を考えてみてください。
広島大学医学部
最初に紹介する広島大学医学部は、国立医学部の中でもっとも理科の配点が高い大学です。
二次試験は理科の他に英語と数学が出題されますが、配点は数学・英語が各300点なのに対し、理科はなんと1200点もあります。
物理・化学・生物の中から2科目の選択式ですが、1科目あたり600点もの高配点比率になっています。
理科2科目で3分の2を占めますので、得意な人なら大きく点を稼げます。
試験時間は2科目で120分ですが、問題数はかなり多いので時間配分に気を付けましょう。
物理は電磁気と力学が毎年必ず出題され、そのほか波動や熱力学が同じ大問で出題される傾向があります。
化学は理論化学と有機化学が大半を占めますが、全科目の中でもっとも難易度の高い科目です。
生物も難易度が高く、遺伝に関する問題が多めに出題されます。
読解力が求められるため、入念に対策しましょう。

引用:https://www.daigakujukennavigator.com/interview/201612_2.html
大分大学医学部
大分大学医学部の二次試験は、4科目+面接で配点が600点となっていますが、理科の配点率が高く、2科目で200点ほどあります。
他の科目は数学と英語で、それぞれ100点配分されていますが、学科に限れば半分を理科2科目が占めています。
ただし、面接の配点が200点もありますので、学科だけでは限界があることに注意してください。
理科の試験は2科目の選択式で、試験時間は合計120分です。
どの科目も医学部専用問題で構成されていて、難易度が高めになっています。
なお、物理は力学と電磁気学から出題される確率が高く、記述式問題が多めです。
化学と生物も難易度が非常に高いうえ、高校の履修範囲からまんべんなく出題されます。
特に物理の記述問題はやっかいなので、時間配分に注意しましょう。
鹿児島大学医学部
鹿児島大学医学部の二次試験は、理科・数学・英語の合わせて800点と、面接の120点で構成されています。
面接の配点も高めですが、学科試験で点数を稼ぐことになるでしょう。
配点は数学・英語が各200点で、理科は2科目で400点となっています。
理科で半分の配点比率を占めますが、逆にいえば50%しかありません。
他の科目はもちろん、面接も重要な得点源と考えるべきです。
試験の難易度はやや高めで、特に化学は記述式の問題が多く、難易度が高い科目となっています。
一方、物理は力学を中心に幅広く出題する傾向にありますが、難易度は化学よりも優しめです。
基礎ができていれば点を落とすことはありません。
生物も同様で、難易度は一般的な医学部レベルといえます。
ただし、記述・論述問題が多いため、時間を取られないよう注意してください。
引用:https://www.edubal.net/edublog/b20180507-17280/
帝京大学医学部
帝京大学医学部は少し特殊です。
必須科目の英語に加え、理科・数学・国語の中から2科目選択する方式になっているので、自分の得意科目を選べます。
各科目は100点満点で、仮に理科を2科目選んだ場合、理科のみで配点比率が3分の2にもなります。
逆に理科を選択しないというパターンもありますので、理科が不要な大学ともいえますね。
試験時間は1科目60分、2科目計120分です。
難易度は標準レベルですが、選択科目によって問題数が多くなります。
物理は力学や原子分野からの出題が多いものの、記述式問題が中心になっています。
生物も難易度は標準レベルですが、バイオテクノロジーなど最新の分野から出題されることもあります。
問題は化学で、出題される問題数が多いため、時間配分に注意しないといけません。
高校の全範囲から出題される傾向にあるため、しっかり勉強して挑みましょう!
自治医科大学医学部
自治医科大学医学部の二次試験は、物理・化学・生物の中から2科目を選ぶ選択式と、数学・英語の4科目で構成されています。
各科目の得点配分は25点で、4科目合計100点となっています。
理科2科目50点と配点比率が高めで、半分もウェイトを占めているのが特徴です。
ただ、数学と英語も合計で50点なので、この2科目も点を落とさないよう気を付けましょう。
試験時間は2科目80分ほどで、難易度も標準的です。
各科目は25の少問で構成されているため、時間配分を考えながら解いていく必要があります。
物理は原子を含めた全範囲から幅広く出題される傾向がありますが、問題数が多いので注意しましょう。
生物は基礎がメインで、化学は有機化学が大半を占めています。
いずれも基礎が問われるので、教科書の範囲をみっちり学習すれば、大きく得点を落とす可能性は低いです。
ただし、気を抜かないようにしましょう。