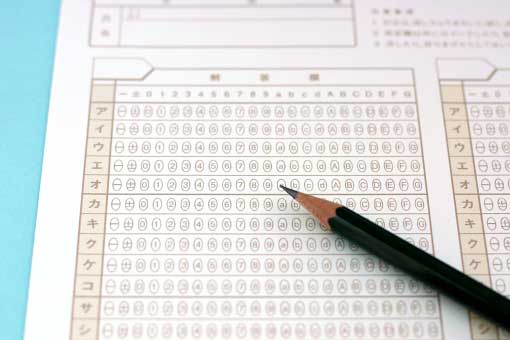
大学入学共通テストとは?
毎年1~2月頃に行われる大学入試ですが、試験といえばほとんどの人はセンター試験を思い浮かべるのではないでしょうか?
これまで何十年も実施されていましたし、私立の医学部志望の人でも、一部はセンター併用で受験することができました。
しかし、今後はセンター試験が終了し、「大学入学共通テスト」という新しい方式の試験が実施されます。
でも、ニュースなどでよく耳にはしますが、どんな試験なのでしょうか?
この記事ではセンター試験との違いと、科目別にどう変わるのかについて解説していきます!
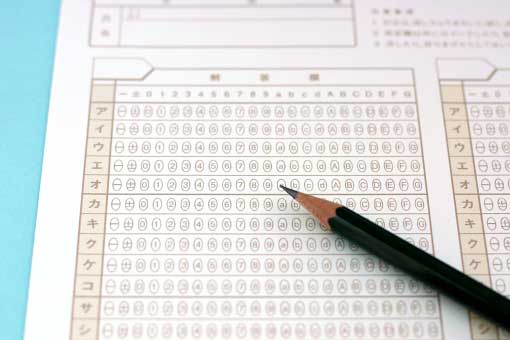
センター試験にかわり導入が予定されている大学の共通入学試験のこと
大学入学共通テストは、今後導入が予定されている大学共通の試験のことです。
プレテストが実施された際には、多数の高校が参加しました。
大学入試というと、これまではセンター試験がその役割を担っていましたが、今後は大学入学共通テストへ完全に置き換えられる予定になっています。
ただし実施する団体に違いはなく、センター試験と同じく独立行政法人大学入試センターが行います。
テレビなどでも度々取り上げられていますが、いろいろな点が変更されるので注意してください。
特に次の3つは大きく変わるので、しっかり覚えておきましょう!
- 一部で記述式問題が加わる
- 平均点が下がると考えられる
- 英語・数学・国語の3科目は大幅な変更がある
一部の科目に記述式の問題が加わるほか、想定される平均点が大きな変更点です。
また、英数国の3科目は大きな変化があります。
後述しますが、変更点を押さえて対策を行いましょう。
全問マークではなくなる
大学入学共通テストで一番大きな変更ともいえるのが、記述式問題が導入されることです。
センター試験は全問マーク式で、解答シートを塗りつぶしていくのみでした。
そのため、残り時間にさえ注意すれば何とかなったのが実情です。
でも、大学入学共通テストではそう簡単にいかなくなります。
答えなどを記入する記述式問題が導入されるため、時間配分の計算が重要です。
マーク式は解答を選ぶのみで済むため、時間もさほどかかりません。
一方、記述式は解答を導くのに時間がかかるので、残り時間との戦いになります。
今後は問題集などでたくさん記述式問題を解き、かかった時間も計測してみることをおすすめします。
平均点はセンター試験よりも下がるという予想が出ている
平均点も下がると考えられています。
今までのセンター試験は、平均点を約6割と想定して問題を作成していました。
このため、6割取れれば十分で、大学の難易度によっては余裕で合格できました。
では、大学入学共通テストはどうかというと、実はセンター試験よりも平均点が低くなると考えられています。
平均点は5割くらいを想定しているようです。
センター試験より予想平均点が下がりますので、一見メリットが大きいように思えますよね。
平均点が下がれば、合格に必要な得点率も下落すると考えられるので、医学部志望の人には有利に働くかもしれません。
しかし、試験問題そのものの難易度が上がるかもしれないので、あまり安心はできないです。
また、上で触れたように記述式問題が実施されますので、科目によっては5割キープすら困難かもしれません。
このため、記述式の問題も極力落とさないように注意する必要があります。
特に大きく変わるのは英数国
大学入学共通テストになっても科目の変更はありませんが、一部は試験の内容がこれまでとは別物になります。
特に気を付けておきたいのが英数国の3科目です。
これらは暗記のみに頼りづらくなりましたので、勉強方法や受験対策も変えないといけません。
英語に関してはリスニングが問題になるため、空き時間を活用して対策する必要があります。
一方で理科は特に変更がありません。
これまでどおりの出題方式なので、勉強方法も変えずに済むでしょう。
センター試験用の参考書も十分試験対策に使えます。
英語
一番変わるといってもいい科目が英語です。
特にリスニングが苦手な人は注意しておきましょう。
センター試験より難しくなると考えて差し支えありません。
ちなみに大きな変更点は次の3つです。
- 筆記がリーディングに名称変更される
- リスニングとリーディングが同じ配点になる
- リスニングは問題によって1回読みになる
筆記がリーディングに名称変更されますが、受験生に何ら影響がありません。
しかし、問題は2つ目と3つ目です。
センター試験では、筆記(リーディング)が200点、リスニングが50点という得点配分でした。
大学入学共通テストでは、これが同一配分になり、各100点(200点満点)へと変更されます。
センター試験でのリーディングは原則2回読みでしたが、1回読みの問題も混ざるようになります。
そのため、今までより入念に対策する必要があります。
なお、リーディングは英単語の暗記や文法の学習で対策できます。
リーディングは、日頃から英会話や英語音源を聞き、英語耳を育てていきましょう。
CD付きの英語の参考書を買ったり、英会話アプリなどを駆使して勉強してすることをおすすめします。
数学
数学の場合、センター試験は答えを選ぶのみだったため、公式などを暗記すればある程度点を取ることができました。
でも、大学入学共通テストでは次のような変更が行われます。
- 記述式問題が導入される
- 試験時間が70分になる
変更点は少ないんですが、記述式問題が導入される点に気を付けてください。
大学入学共通テストでは、数学ⅠAを除いて記述式問題の導入が予定されています。
これまでのように暗記一本勝負とはいかず、学習方法も変えなくてはいけません。
特に読解力や倫理的な思考力が試されますので、演習問題をこなして感覚を磨きましょう!
一方、試験時間が60分から70分に変更されます。
試験時間が伸びるのは嬉しいですが、記述式問題があるため、時間配分には気を付けないといけません。
やはり演習問題の数をこなし、短時間で解けるよう練習することが大切です。
タイマーやアラームを使って、本番さながらの状況を作るのもいいでしょう。
いずれにしても、記述式問題は時間との戦いです。
マーク式問題に時間を取られると、焦って点を落とす可能性があります。
繰り返しますが、素早く解けるように何度も練習しましょう。
国語
そして最後の国語ですが、こちらも以下のような変更が行われます。
- 記述式問題の導入
- 試験時間が80分に延長される
変更点は数学とまったく同じで、記述式問題の導入が大きな変更点です。
試験時間も伸び、60分から80分に延長されます。
ただ国語は考察や洞察、読解力などが幅広く試される科目です。
日頃から勉強していないと、本番で点を大きく落とすかもしれません。
しかし医学部志望の人は、他の科目を重視するのもおすすめです。
確かに記述式問題の練習をして、時間配分などの練習をすることも大切。
でも、国語に勉強時間を割いても、他の科目が疎かになるおそれがあります。
国語は点を落とさないよう最小限の勉強にして、他の科目で点を稼いだほうがいいです。
記述問題の導入に関しては2021年度は見送りが確定している
大学入学共通テストは記述式問題が非常にやっかいですが、2021年度の実施については見送りが確定しているんです。
つまり最短で2022年からの実施が予定されています。
2021年の受験生は、記述式問題の影響を受けずに済みます。
でも、2022年度も見送りになる可能性は否定できませんし、試験直前に変更されるパターンも考えられます。
やはり記述式の採点がネックになっている模様です。
今後しばらくは注視したほうがよさそうですね。
まとめ
大学入学共通テストについての解説でしたが、ポイントをまとめますね。
- センター試験の代わりに導入される試験
- マーク式に加え記述式問題が追加
- 平均点の想定は5割程度になる
- 英国数は大幅に変わる
- 英語はリスニングの配点比率が5割に
- 数学と国語は記述式問題を導入
特に英語のリスニングと、記述式問題の導入が大きな違いです。
どちらもぶっつけ本番は難しいので、しっかり対策して挑みたいところです。


